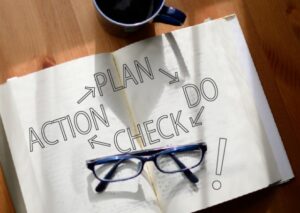第6章 評価制度を文化にする ― チームで育てる職場づくり
「せっかく作った評価制度が、現場に根づかない」。
これは、多くの事業所が抱える悩みの一つです。
制度の内容がどれほど優れていても、現場の一人ひとりが納得し、日常の中で自然と活用されるようにならなければ、長くは続きません。
つまり、評価制度は“導入する”だけでなく、“職場の文化として育てていく”ことが大切なのです。
特に、職員数が20名前後の小規模な福祉・介護事業所では、制度の成否は「リーダーの関わり方」と「チーム全体の理解」に大きく左右されます。
この章では、評価制度をチームで共有し、現場の文化として定着させるための実践的な視点をお伝えします。
●リーダーの意識が職場を変える ― 評価は“伝える”から“育てる”へ
評価制度の定着を語る上で、まずカギになるのは、リーダーや管理者の姿勢です。
制度の使い方だけでなく、「評価とは人を育てるためのもの」という意識を持てるかどうかで、現場の空気はまったく違ってきます。
たとえば、評価面談を事務的に済ませてしまうリーダーと、日々の何気ない行動に目を向け、「この前の対応、すごくよかったよ」と声をかけるリーダーでは、職員の受け取り方が全く異なります。
また、リーダー自身が「フィードバックを受け取る側の姿勢」も見せることが大切です。
職員からの意見や提案に耳を傾け、自分も学ぶという姿勢がある職場には、自然と「成長を応援し合う文化」が育ちやすくなります。
●共通の“ものさし”を持つ ― チームで評価基準を共有する
評価における“モヤモヤ”の原因の一つは、評価者によって判断基準が違ってしまうことです。
小規模な現場では特に、スタッフ間での関係が近いため、「どうしてあの人は評価が高いの?」という不公平感につながりやすくなります。
こうした問題を防ぐには、チーム全体で評価基準を共有する機会を設けることがとても重要です。
たとえば、月1回のリーダー会議で
「この項目ってどんな行動が対象になる?」
「このケースではどう評価する?」
と話し合う場を持つことで、評価の“ブレ”を減らし、納得感のある制度運用ができます。
また、定性評価(数字にならない行動評価)についても、できるだけ具体的な「行動例」をすり合わせておくと、どの評価者が担当しても職員に一貫性のあるフィードバックができます。
●制度を“育てる”仕組みをつくる ― 継続的な見直しと関わり
どんなに良くできた制度でも、運用していくうちに必ず「現場に合わない部分」や「変化するニーズ」が出てきます。
だからこそ、評価制度は一度作って終わりではなく、「チームで育てていく」意識が必要です。
具体的には、年に1回の評価制度見直し会議を設け、職員の声を反映させることが効果的です。
「この評価項目が曖昧で分かりづらかった」
「もっとこんな視点も入れてほしい」
といった現場からの意見は、制度改善の宝の山です。
また、制度をうまく活用している職員の取り組みを全体で共有するのも効果的です。
たとえば、「〇〇さんのフィードバックのやり方、参考になった」というように、よい実践をチームで学び合う文化が育てば、制度が“生きたツール”として息づいていきます。
評価制度を“文化”にするとは、誰か一人が頑張るのではなく、チーム全員で制度を理解し、活かしていく関係性を育てることです。
次章では、これまでの内容を振り返りながら、これからの福祉現場に必要な“人を育てる評価制度”のあり方について、改めてまとめていきます。