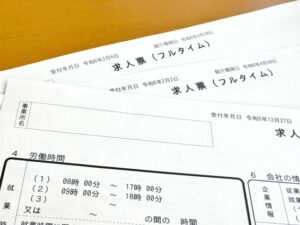第3章:面接で“人となり”を見抜く
――「感じが良さそう」だけでは、うまくいかない
「面接では感じが良かったんです。でも、入ってみたら全然違って…」
そう話すのは、飲食店を経営するTさん。
スタッフはアルバイトを含めて10名ほど。地元密着型のお店です。
あるとき、ホールスタッフの欠員が出たため、Tさんはハローワークに求人を出しました。
応募してきたのは、30代の男性。面接ではハキハキと受け答えし、笑顔も爽やか。
「この人なら、お客様にも好印象を与えてくれそうだ」
そう感じたTさんは、即採用を決めました。
ところが――
入社して1週間も経たないうちに、スタッフとのトラブルが続出。
「自分のやり方が正しい」と主張し、先輩の指示を無視。
注意すると逆ギレし、職場の雰囲気は一気に悪化しました。
「面接の印象だけで判断したのが間違いだった」
Tさんは、採用のやり方を根本から見直すことにしました。
●面接は「感覚」ではなく「設計」で決まる
Tさんが最初に取り組んだのは、採用基準の明文化でした。
「うちの店で働くうえで、絶対に外せない条件は何か?」
スタッフとも話し合い、次のような基準を定めました。
- チームで協力できる人
- 指示を素直に受け入れられる人
- お客様に対して丁寧な対応ができる人、笑顔が素敵な人
- 採用後に自社で育成できない能力(例:向上心)がある場合は採用しない
さらに、「このような事実がある場合は採用しない」という“NG条件”も明確にしました。
たとえば、過去に職場での人間関係トラブルが複数回ある場合や、指示に従うことが極端に苦手な場合などです。
次にTさんは、面接で使う質問集を作成しました。
これまではその場の雰囲気で質問していたため、求職者によって聞く内容がバラバラ。
それでは比較もできず、判断もブレてしまいます。
そこで、採用基準に沿って、次のような質問を事前に用意しました。
| 採用基準 | 質問例 |
|---|---|
| チームで協力できるか | 「これまでにチームで働いた経験はありますか?どんな役割でしたか?」 |
| 指示を受け入れられるか | 「上司や先輩と意見が合わなかったとき、どう対応しましたか?」 |
| 丁寧な接客ができるか | 「お客様からクレームを受けた経験はありますか?どう対応しましたか?」 |
| トラブル傾向の有無 | 「これまでの職場で、どんな人と合わなかったですか?なぜそう感じましたか?」 |
このように、「何を知りたいか」→「どんな質問をするか」を明確にすることで、面接の精度が格段に上がりました。
●「職場見学」と「実務体験」で“本音”が見える
さらに、Tさんは、面接のあとに職場見学を取り入れました。
たとえば、ホールの邪魔にならないところに立ってもらい、スタッフの動きをみてもらう。
その後、求職者に感想を聞き、その反応から求職者の仕事に対する熱意や姿勢などを探っていきます。
求職者にとっても、「実際の仕事がどんなものか」を体感できるため、
「思っていた仕事と違った」というミスマッチを防ぐことができます。
また、Tさんは、面接に現場のリーダーや先輩スタッフにも同席してもらうようにしました。
経営者だけでは見抜けない部分も、現場のスタッフなら気づけることがあります。
求職者にとっても「どんな人と働くのか」が分かるため、安心感につながります。
実際に、スタッフから「この人なら一緒にやっていけそう」と意見が出た人は、入社後も定着率が高い傾向にありました。
Tさんは、事前に求職者と合意を得たうえで行うことを前提に、採用時に有期雇用契約(たとえば1〜3ヶ月)を結ぶことにしました。
これは、求職者と会社の双方にとって「お試し期間」として機能します。
この期間中に、実際の仕事ぶりや職場への馴染み方を見て、事業主・労働社がお互いに「このまま長く働いてもらえるかどうか」を判断します。
●適性検査は“補助ツール”として使う
Tさんは、適性検査も導入しましたが、あくまで補助的な情報として活用しています。
たとえば、検査で「協調性が低い」と出た場合でも、面接や実務体験でその人の行動を見て判断します。
「検査結果だけで判断していたら、良い人材を見逃していたかもしれない」
そう語るTさん。
適性検査は“面接で確認すべきポイントを絞るヒント”として使うのが正解です。
こうした取り組みを始めてから、Tさんの店では採用後のトラブルが激減しました。
最近採用した20代の女性スタッフは、未経験ながらもチームにすぐ馴染み、
今では常連のお客様からも名前で呼ばれるほど信頼されています。
「面接は、感覚じゃなくて“設計”なんだと実感しました」
そう語るTさんの表情は、以前よりもずっと自信に満ちていました。
《まとめ》
- 面接は「感覚」ではなく「設計」で精度が上がる
- 採用基準を明確にし、「この事実がある場合は採用しない」を決めておく
- 採用基準に基づいた「質問集」を準備することで判断がブレない
- 職場見学や実務体験で、求職者に仕事を“体感”してもらう
- 面接には現場の上司・先輩・同僚も同席し、複数の視点で判断する
- 有期雇用契約で“お試し期間”を設け、お互いのミスマッチを防ぐ
- 適性検査はあくまで補助ツール。面接や実務体験での観察が最重要
- 自社で育成できない能力が必要な場合は、採用しない判断も必要
次章では、採用した人材が「辞めない」「育つ」ための育成と定着の工夫についてお話しします。
せっかく採用した人材を、どうすれば長く活躍してもらえるのか――
中小企業でもできる「辞めない職場づくり」のヒントをお届けします。